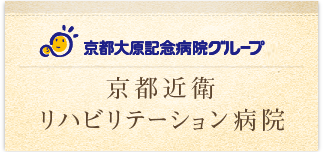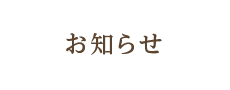【第八報】 新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴う対応状況について
2020年4月18日(土)18:00 新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴う対応状況について 手指消毒、不要不急の集まりへの参加等の自粛、などの予防に加え、以下の通り感染拡大予防に向けた取り組みを実施しております。 ■面会禁止の実施[実施]2月25日(火)~ ※2月21日(金)面会制限 → 2月25日(火)面会禁止 ①お見舞い・面会禁止 ②患者様・ご利用者の外出・外泊禁止とさせていただいております。 ■スタッフ全員を対象とした、出勤日毎日の体調確認[実施]3月1日(日)~ 体温測定結果等は所定の体調管理表に記録し、所属長が管理しております。なお、37.5℃以上の発熱や呼吸器症状(のどの痛み、咳、鼻水、だるさなどといった症状)がある場合は、新型コロナウイルス感染症の診断がつかなくても自宅待機しております。 ■国内外の旅行の禁止 [実施]3月12日(木)~ 医療機関として私生活においても最大限感染拡大を予防する意味から禁止。また業務上では出張、及び外勤(法人事業所外での勤務)も原則禁止。 ■1日3回以上の換気 [実施]3月19日(木)~ 各施設で徹底し、その旨を館内放送でもアナウンスしております。 ■シャトルバスの環境衛生の徹底 [実施]4月2日(木)~ 1日2回全座席を環境清拭ワイプ(クリネル)で拭き上げ、換気のため窓を開けて運行します。 ■大原井出ゾーン施設における通所サービス利用者の利用エリア制限[実施]4月6日(月)~ 特別養護老人ホーム 大原ホーム デイサービスセンター、介護老人保健施設 博寿苑 通所リハビリテーション利用者と、施設内入所者が同一空間に混在することを回避するため導線に制限を設けます。 ■シャトルバスの減便 [実施]4月9日(木)~ 上記環境衛生を一層徹底するため、一部欠便して運行いたします。また引き続き、換気のため窓を開けて運行します。※欠便対象はこちら(時刻表へリンク)をご確認ください。 ■体調管理における自宅待機の基準を厳格化[実施]4月18日(土)~ 感染拡大予防に向けて一層院内の意識を強化する意味合いからスタッフの体調管理(体温測定)における、自宅待機の基準を厳格化します。従来「37.5℃以上」としていたところを、今後「37.0℃以上」とします。そのほか、呼吸器症状(のどの痛み、咳、鼻水、だるさなどといった症状)がある場合も引き続き自宅待機といたします。 [お願い]面会禁止の「継続」について 新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大予防策として実施しております「面会禁止」の対応を、2020年4月1日(水)以降も「継続」することといたしましたのでご案内します。ご迷惑をおかけいたしますが、患者様をはじめとした、ご利用の皆様に安全な療養環境をご提供するための措置として引き続きご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。 なお、京都大原記念病院グループ関連施設内に於いては感染者の発生など、直接的な影響は発生しておりませんことを合わせてご案内します。ご家族の皆様におかれましてはどうぞご安心ください。引き続き、感染予防に努めて参ります。 マスクについて 報道等にもありますように、引き続き日本国内において「マスク」が不足している状況です。京都大原記念病院グループ各施設でも、この状況を鑑み「呼吸器症状のある方」「医療行為(処置など)の感染防御策として必要な場合」など優先順位に基づき使用しております。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 新型コロナウイルス(COVID-19)関連 _参考情報 新型コロナウイルス(COVID-19)感染が確認された方が、連日100名超増加するなど、その動向に予断を許しません。以下の目安に当てはまる場合は以下の専用相談窓口にご相談ください。当てはまらない場合は、「手洗い」「うがい」「不要不急の外出の自粛」など、ご自身で取り組むことができる予防に努めてください。 [相談の目安] ■風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。 (解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます) ■強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。 (高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合) [相談窓口] 厚生労働省電話相談窓口(web) 9時~21時(土日・祝日も実施) 0120(565)653 京都市 電話相談窓口(web) 土・日・祝日を含む24時間 075(222)3421 京都府 電話相談窓口(web) 平日・土・日・祝日 24時間対応 075(414)4726 感染予防のお願い 新型コロナウイルス(COVID-19)に限らず、インフルエンザ等の呼吸器疾患の感染症対策は「かからない」「うつさない」ことが大切です。手洗い、咳エチケット、正しいマスク着用のほか、栄養と休養を十分にとり体力低下を予防しましょう。また3つ密を避けて行動しましょう。 出典:首相官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/jp/content/000059525.pdf) 出典:首相官邸ホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/content/000061868.pdf) 上記内容は2020年4月18日(土)18:00時点の情報です。今後も厚生労働省等から発表される最新情報等に基づき対応いたします。 なお、更新情報がある場合には当ページでご案内いたします。ます。情報は随時更新・ご案内して参ります。ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。 【過去の対応状況】 第七報(こちら)2020年4月6日(月)12:00時点 第六報(こちら)2020年4月2日(木)12:00時点 第五報(こちら)2020年4月1日(水)12:00時点 第四報(こちら)2020年3月19日(木)17:00時点 第三報(こちら)2020年3月11日(水)9:00時点 第二報(こちら)2020年2月25日(火)19:00時点 第一報(こちら)2020年2月21日(金)17:00時点 京都大原記念病院グループ 感染対策委員長 2020年4月18日(土)18:00