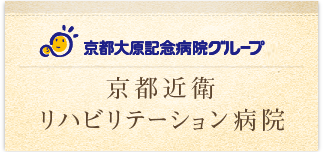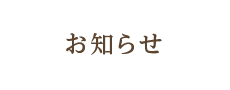日々提供するリハビリテーション医療がより良いものとなるよう、様々なテーマで各職種が研鑽に努め、学会などでの外部発表などに取り組んでいます。本日はその一例として当院の看護師(所属は発表当時)が発表した「 NICD(生活行動回復看護) 」をテーマとした演題をご紹介します。多職種のチームで連携し、症状の悪化を防ぐことができた症例について報告しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
肺野への微振動を与えることの効果について
~重症肺炎にチームで取り組んだ一症例~
吉田実紅(京都大原記念病院 看護師)※研究当時の所属
第14回日本ヒューマン・ナーシング研究学会 2018年10月
はじめに
重症肺炎、無気肺※1を発症し人工呼吸器を装着された患者Aさん(50代後半・男性)に対し、肺本来の機能や仕組みの復活を期待し、肺への微振動を実施しました。今回はNICDを導入し、看護計画にもとづいて気道の浄化を積極的にし、また療法士との呼吸理学療法や、多職種チームでのアプローチを実践したことにより症状の悪化を妨げた症例を経験しましたので報告します。
生活行動を自立へと導くNICD(生活行動回復看護)
患者様のできることを引き出す
症例は当初、脳出血後遺症のリハビリテーション(以下、リハビリ)を目的として入院されましたが、胆のう炎を併発したことから、一時転院となり、治療を経て再度リハビリ目的で入院されました。再入院当時、両側肺炎、無気肺※1となっていたことから、人工呼吸器を装着することとなりました。主治医からは薬物治療、呼吸理学療法と同時にNICD※2開始の許可が出ました。
NICD※2導入にあたり、まず患者家族へは技術の内容と何らかの悪化のきざしを認めた場合はただちに中止し、主治医が対応することを説明、同意を得て、2017年4月~2017年8月の間に実施することとしました。
個別メニューを作成し、NICD※2研修を受講した看護師を中心に理論や実技について病棟内の他スタッフを指導、共有し、統一してできる準備をしました。リハビリを実施する時間を固定し、呼吸理学療法の研修を受けた、もしくは実施経験のある療法士によるリハビリとNICD※2を1日のケア計画の中で効果的に実施できるよう調整しました。受持ち看護師が主体となり、複数人のスタッフで呼吸状態等に注意しながら実施するなど安全面に配慮しながら取り組みました。
安全に最大限配慮し、
バランスボールを用いて微振動を実施
具体的な個別メニューは以下の通りです。
バランスボールを用いて、股関節や骨盤底筋群※3を柔軟にした後、頭の位置を調整して体幹の並びを整え※4、座る姿勢への体位変換の準備をする(図1)
[caption id="attachment_285" align="alignnone" width="300"] 図1[/caption]
胸郭運動に必要な胸の筋肉にバランスボールを用いた微振動により刺激を与える(図2)
[caption id="attachment_286" align="alignnone" width="300"] 図2[/caption]
半腹臥位に変え※5、バランスボールを用いて背中から微振動により刺激を与える(図3)
[caption id="attachment_287" align="alignnone" width="300"] 図3[/caption]
3.の姿勢で、足の裏へも同様に微振動を行い脳へ刺激を与える(図4)
[caption id="attachment_288" align="alignnone" width="300"] 図4[/caption]
入院時、A氏は両側肺炎と無気肺※1の状態で他の呼吸疾患も併発されていました。当時の検査では、白血球数が異常値(WBC※6 12,400/µL・成人の基準値:4,000~9,000/µL)を示し、また必要な栄養素が不足している状態(アルブミン値2.7・低栄養)でした。
入院3日目からNICD※2の介入は入院3日目から開始し、療法士による呼吸理学療法と同時にバランスボールによる微振動を実施しました。
入院5日目には個別メニューを作成し、病棟スタッフ間で共有し、以降は毎日実施しました。
こうした経過を経て、入院8日目には無気肺※1が改善され、2週間目には人工呼吸器を離脱、インスピロン※7へ変更することとなりました。この時点での白血球数(WBC※5 )7,200/µL、アルブミン値 3.2、血中の酸素濃度を示すSpO2 は100%となりました。白血球数、血中の酸素濃度はいずれも正常値内。栄養状態も低い水準ではありましたが改善が見られました。
苦手意識もあったが、正しく状態を理解し、
チームでアプローチした結果状態は改善
呼吸には基本的に重力に拮抗した姿勢(直立)を保つことが一番いいとの報告があります。寝かせきりになると呼吸機能の低下は避けられません。今回のように人工呼吸器を装着されている場合などは特にできるだけ背面
を支持しない空間をつくることが呼吸を助けることになります。
また、急激に状態が悪化した時に呼吸ケアを早期、かつ様々な職種がチームとして介入することで、たとえ人工呼吸器装着となっても早期の離脱や二次的障害発生率が下がり、入院日数の短縮が図れたとの報告もなされています。
これまでは人工呼吸器に対し、苦手意識や体を動かすことへの恐怖があり積極的に介入できませんでした。しかし、今回の症例では看護師が中心となって状態を理解し、早期段階から背部への微振動や、療法士らと協同で呼吸理学療法を実施できました。その結果、酸素化が良好となり、痰の排出を促すことで気道の浄化を効果的に行うことができました。また、経鼻チューブからの栄養投与を続けたことで栄養状態が改善し、水分補給もできたことで痰がベタつかず吸引しやすい状態であったことから気道を清潔にすることが出来ました。
治療の効果に加え、早期介入により、血液に酸素が取り込まれやすくなり、無気肺※1の改善と約2週間での人工呼吸器離脱を果たすことができました。チームで集中的に介入し、的確に呼吸状態を観察、評価しながら、呼吸の介助とNICD※2を計画的に実践したことが状態の改善につながったと考えています。
より一層、チームで取り組む
NICDの実践へ
看護師は患者の身体の仕組みを知ったうえで障害された機能を代償する・改善できる方法を探します。保健師助産師看護師法では、看護師の業務は「 診療の補助と身の周りの世話 」とされています。これをどのように行うかは自分たちがしっかり考え、実践しなければなりません。私たち看護師の目や手はそれを見つけ、手当てするためにあります。今後、ますますNICD※2により身体の状態が改善され、苦痛から解放される患者さんを増やしていくためチームで取り組んでいきたいと思います。
抄録はこちら
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※1:無気肺
空気をうまく取り込むことができず、肺がつぶれてしまっている状態
※2:NICD(Nursing to Independence for the Consciousness disorder And the Disuse syndrome PAtient)
看護手技の一つで患者の生活行動回復看護と定義されています。主に寝たきりや、廃用症候群の患者様の身体的変化を生理学的、病理学的視点からアセスメントを行い、生活行動を自立へと導く、いわば患者様のできることを引き出すことを目指す看護です。
※3:骨盤底筋群
骨盤を覆うように骨盤の底部分に位置する筋肉
※4:体幹アライメント
姿勢分析や動作分析などを行なうときの指標・評価の対象。体幹アライメントの失調とは体幹(脊柱)にねじれや左右差があり垂直ラインが乱れている状態。麻痺側の筋緊張の低下から非麻痺側での過剰努力による固定が強まり、左右差がみられる。このために上手く非麻痺側上肢が使えず車椅子の自走や食事がとれなくなること。
※5:半腹臥位
抱き枕に覆いかぶさるような姿勢(イラスト参照)。人工呼吸器を装着されていたため、体位変換は2人以上で行い気道確保の確認、気管挿管チューブの深さや位置、患者の表情や状態を確認しながら、同時に吸引の準備もして行いました。
※6:WBC(white blood cell)
白血球数。個人差が大きく、また同じ人でも1日のうちに数値は大きく変動するが異常値時には様々な疾患が考えられる。高値の時に考えられる疾患に肺炎などがある。
(参考)基準値
成人
4,000~9,000/µL
小児
6,000~10,000/µL
幼児
6,000~18,000/µL
新生児
9,000~25,000/µL
※7:インスピロン
ベンチュリーマスクのことで、マスクのように装着して使用します。一定の酸素濃度を維持しながら酸素を送ることができる機器となります。
続きを見る