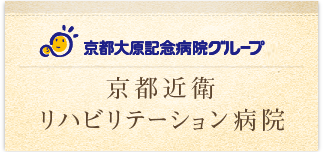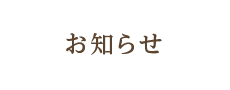当院は間もなく開院から1年半を経過します。患者様からも、連携医療機関からも、スタッフからも「選ばれ続ける病院」であるために始動した新しい動きを 児玉直俊医師(院長補佐)がご紹介します。
【INDEX】
>■気が付けば開院から1年半
>■より良い病院を目指して理想と課題を多職種で共有
>■「ホスピタリティー」「教育」「連携病院」、病院として標準化を
>■理想の病院を目指してまずは一歩踏み出す
気が付けば開院から1年半
京都近衛リハビリテーション病院はグループとして本院(京都大原記念病院)以来の病院拠点として2018年4月に開院しました。開院当初は、診療の方針や進め方、病棟やカンファレンス運営、職種間の連携、スタッフの働く環境、各種備品の運用ルールなどなど、あらゆることを一から作り上げる日々はとても慌ただしいものでした。気が付けば開院から1年半が過ぎようとしています。
当院に関わる全ての方のご協力をいただきながら、今日まで大きな事故なく運営することができ、一定の御評価をいただくようにもなってきました。しかし我々としてはまだまだ課題は多く、一度このタイミングで病院スタッフが現状の課題把握と目指すべき方向性の確認や意思統一をする事が必要なのではないかと考え、今後当院がより良い病院となるためにミーティングを始動しました。
[caption id="attachment_345" align="alignnone" width="350"] 筆者(児玉直俊・医師)[/caption]
より良い病院を目指して理想と課題を多職種で共有
患者様からも、連携医療機関からも、スタッフからも「選ばれ続ける病院」であるために、各職種の管理職を中心に「病院の理想像」について議論しました。院内スタッフの一人ひとりが同じ価値観を持ち、同じ方向を向いて団結し、成長していくためにはどうすれば良いかを話し合いました。「大原(本院)がこうしているからこうだ」だけではなく、自分たちで考え決定し、現場に浸透させていくにはどうすればいいかという視点を重視しました。
議論に先立ち、まず現場の中堅以上のスタッフに匿名でアンケートを、質問はシンプルに2つに絞って実施しました。1つ目は「どのようなリハビリ病院にしていきたいと思いますか?」2つ目は「(1つめの質問への回答に対し)現状できていること、できていないことは何だと思いますか?」というもの。思った以上に様々な声が集まり、多様な経験を持つスタッフがそれぞれの目線で問題意識を持って取り組んでいることを感じました。
「ホスピタリティー」「教育」「連携」、病院として標準化を
ミーティングでは、まずグループや本院で掲げる理念や行動指針を確認しました。それを参考にしながらも、当院ではどうあるべきか?を考えました。そのうえでアンケートの回答を共有した結果、我々が目指す病院の理想像は「やりがいと活気があり、患者様から選ばれる病院」と設定しました。
医療の専門性の追及は必要です。しかし、まずは組織として「ホスピタリティ」「教育」「(主に院内の)連携」という3つの基盤をしっかりと固めることが重要と考えました。またそれが職種や個人によって差があるのではなく、スキルやレベルを標準化していくことが大切という共通認識にいたりました。この3つを充実させるためにはどうすれば良いか、議論は思いのほか白熱し全三回にわたり意見交換を行いました。
[caption id="attachment_346" align="alignnone" width="350"] (図)3日間の議論ではこれらがテーマにあがった[/caption]
同じ出来事でも、職種や立ち場が違えば感じ方も様々なようでした。院内の「連携」の基本はコミュニケーションです。多職種のチームで取り組むリハビリテーション医療をより良いものとするためにも欠かせない要素です。この点一つをとっても、十分なのかそうでないのかについては人により感じ方が違うことが明確になりました。この点は、スタッフ同士の日頃のあいさつや声かけの程度はもちろん、コミュニケーションの内容や質にも差があり、ひとつの患者情報の重要性の認識にもスタッフ間でギャップがあるようでした。院内連携の話に見えても実は教育に通じる課題であるなど、問題の根幹を明確にする機会にもなりました。
当院では現状、グループとしての各職種別の教育システムに乗せて教育をしているにとどまっていますが、これを期に院内の教育体制を主導する組織として、職域を超えた教育委員会の設置も検討しています。スタッフ個人が院外で得た知識や技術を院内に還元する仕組みを整えたり、接遇や認知症ケア研修などすべての医療人に必要なスキルアップの機会を増やし、病院スタッフ全員のレベルアップを図っていきたいと考えています。これは従来の本院やグループの教育システムと並行して行い、良いものはグループ全体にも還元できればと考えています。
理想の病院を目指してまずは一歩踏み出す
多職種が集って当院の現状を様々な目線から共有できたことは非常に有意義な機会でした。議論を経て、できることから取り組みを始めて行こうとホスピタリティ向上に向けた「地域貢献活動」として、8月から院外清掃活動をスタートしました。今後も定期継続的に各職種が参加して、取り組んで行きます。
今回の過程ではまだ具体化したことは限られていますが、今後も院内でしっかりとコミュニケーションを取り、具体的な実行と定期的な振り返りを実施し、理想として掲げる「やりがいと活気があり、患者様から選ばれる病院」の実現に向けて着実に進んでいければと思います。
今回、このような機会を設けた理由は、病院スタッフに自分達で自分達の病院を作っていくという意識を持って欲しかったからです。どんな仕事であれ、やらされるという意識ではいい仕事ができません。いい仕事ができないと患者さんにいい治療は提供できません。自分たちで決めたことなら責任を持ってやり遂げられるはずです。若い病院であるからこそ、これから作り上げていくことができます。ここで働いてくれるスタッフが将来、自分達で作り上げた病院なんだと胸を張れる病院にしていきたいと思います。
これからもご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
|筆者|
京都近衛リハビリテーション病院 院長補佐
児玉直俊(こだまなおとし)
|資格|
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本リハビリテーション医学会専門医
日本心臓リハビリテーション学会指導士
義肢装具等適合判定医
続きを見る